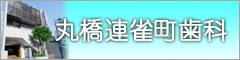1944年群馬県生まれ。東北大学歯学部卒業。同学部助手を経て、1974年、丸橋歯科クリニック開業。1981年、「良い歯の会」活動開始。2004年、群馬県高崎市栄町に「丸橋全人歯科」を開業。現在、丸橋全人歯科院長。日本口腔インプラント学会、日本全身咬合学会会員。日本歯内療法学会認定医。
主な著書に、『癒しの思想』 『全人的治癒への道』 『〈全人歯科〉革命』(以上、春秋社)、『新しい歯周病の治し方』 『歯 良い治療悪い治療の見分け方』 『よくわかる顎偏位症の治療と予防』 『インプラントで安心』 (以上、農文協)、『退化する若者たち』『心と体の不調は「歯」が原因だった!』(PHP新書)、『歯で守る健康家族』(現代書館)、『生きる力 〈いのちの柱〉を取り戻せ』(紀伊国屋書店)、『すいせん村のねこやしき』『エリカのお花ばたけ』(ストーク) など多数。